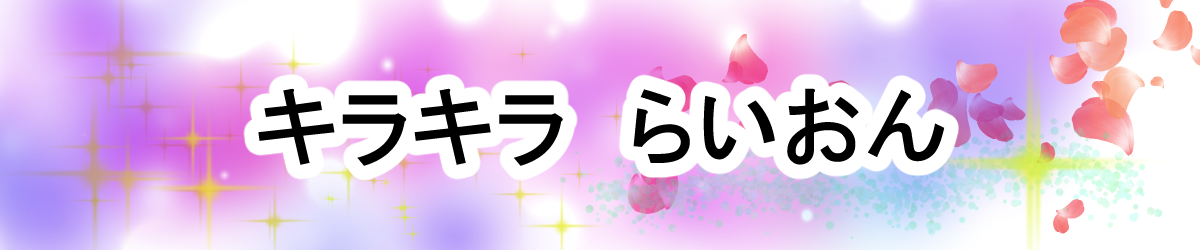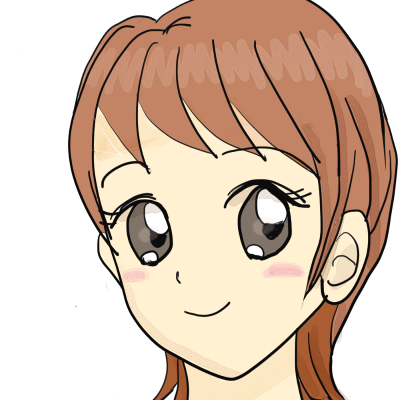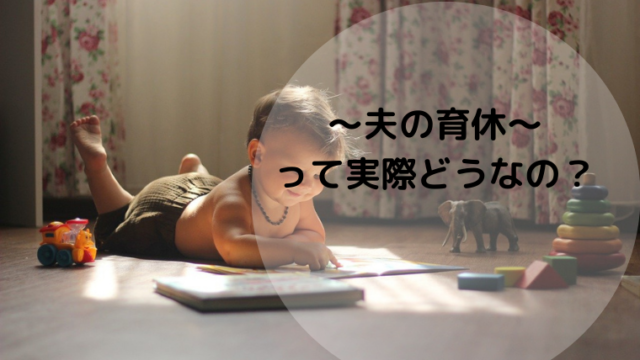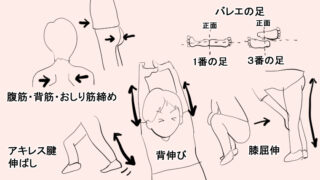2022年10月1日産後パパ育休(出生時育児休業)が施行され、男性育休取得を推進している現在。
しかし、男性の育児休業(育休)取得率は13.97%。男性医師に限ると2.6%。
本記事は「男性育休を取得する方がひとりでも増えれば」という思いで、脳外科医ママ(夫育休経験者)が書きました。
<内容>
✓男性育休の基礎知識
✓男性医師の育休取得率
✓取得率が低い理由
✓問題点と解決策
育休の基礎知識
育休はいつ・どれくらい取れる?
育休は男女ともに、法律で定められている制度。原則1歳未満の子どもを養育する従業員が、勤務先に申し出ることで、利用可能。
男性は、配偶者の出産予定日から子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで取得できます。
<取得できない条件>
・雇用されている期間が1年未満
・1年未満に雇用関係が終了
・週の所定労働日数が2日以下
産後パパ育休(出生時育児休業)
2022年10月1日施行。子どもの出生後8週間以内の間に、育休と別枠で取得可能。
期間内は、4週間までの休業を2回に分けて取得できます。
産後8週間後の育休についても、最長1年間を2回に分けて取得できるように。
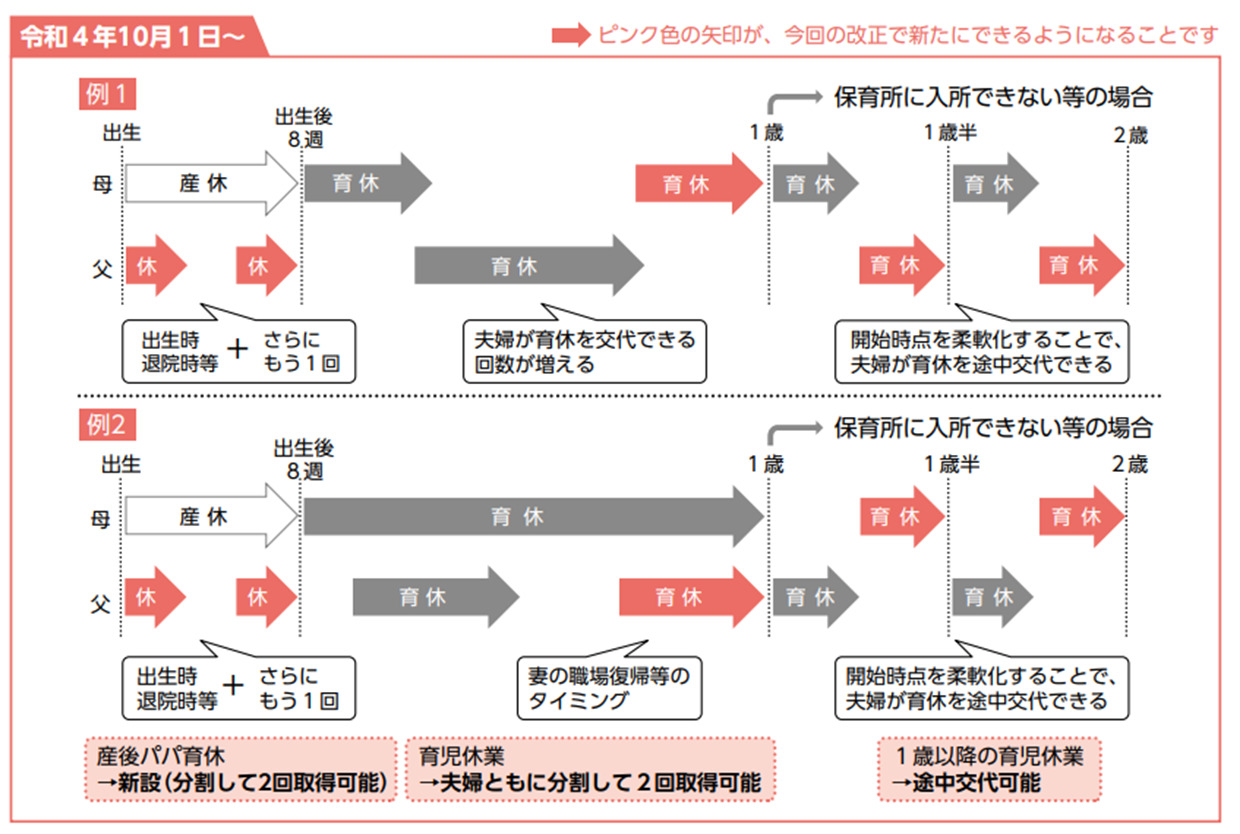
育休の取り方がフレキシブルに
・申し出は、原則休業の2週間前まで
・2回に分割取得する場合、まとめて申し出る必要がある
・希望があれば、休業中の就業が可能(上限あり)
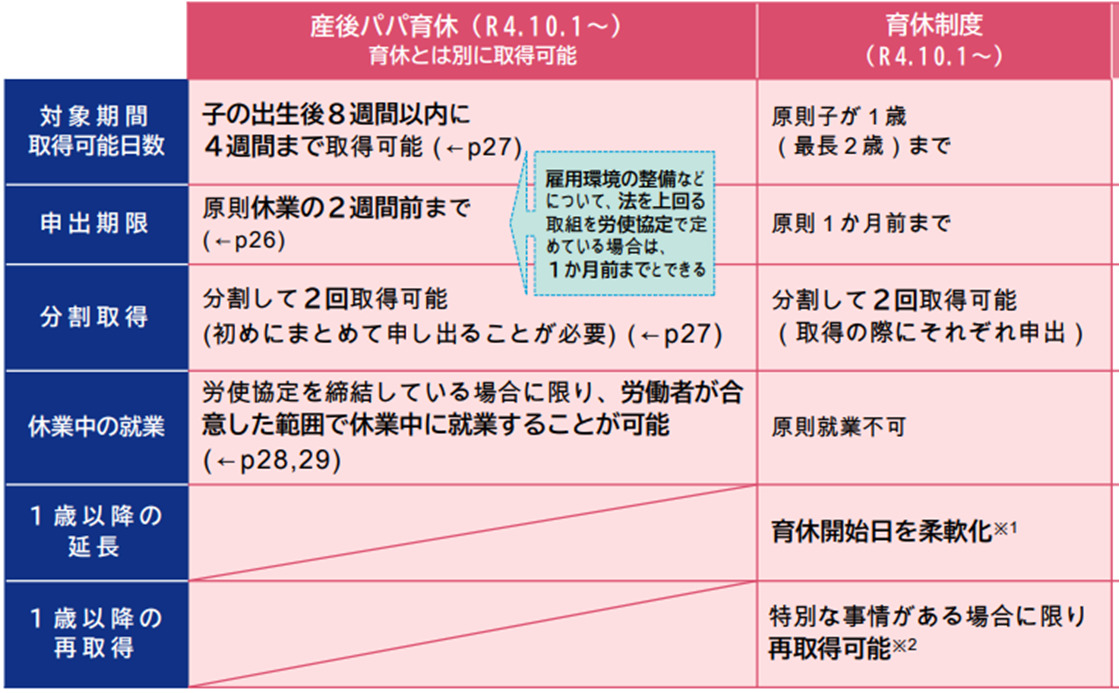
▼さらに詳しく
厚生労働省より
000789715.pdf
マネコミ!より
【2022年最新】男性の育休はじつはメリットだらけ! 取得期間や助成金など、法改正も併せて制度の内容を解説
育休中の給付金
雇用保険に加入している場合、最初の6ヵ月は「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」それ以降は50%。
この給付金からは、税金や社会保険料は引かれないため、給与のおよそ80%を受け取ることになります。
大学院生など対象外になることも。
無給とならないか、申請前に総務課へ確認しましょう。
▼さらに詳しく
Q&A~育児休業給付~
申請の方法
休業開始予定日の1ヵ月前までに申請。(産後パパ育休は、原則休業の2週間前までに)
総務課で必要な書類を確認し、提出します。
男性の育休取得率と期間
2022年男性育休取得率は13.97%。男性医師に限ると、育休取得率は2.6%、非常に低いです。
育休期間は、2週間未満が約5割。1ヵ月~3ヵ月が約25%。
現状は厳しいですね…
▼業種による取得率
令和3年度雇用均等基本調査|厚生労働省
2023年4月から、従業員が1000人を超える企業は男性労働者の育休取得率等の公表が必要です。
取得時期はいつが多い?
子の出生後8週間以内が最多(46.4%)。
この時期は、母体ケアが必要、メンタルが不安定、子どものお世話に慣れない時期なので、女性側としては助かります。
育休期間(2週間未満が多い)をあわせると、ほとんどの方が、「ママ産後のみの短期育休」を取っていることがわかります。
出典:
厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」000851662.pdf
厚生労働省「仕事と育児の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」
0000174276_1.pdf
なぜ取得率が低いか
職場が
・男性育休に対する理解がない
・男性育休を推奨しない
従業員が
・育休に対する知識が少ない
・育休を希望するが利用していない
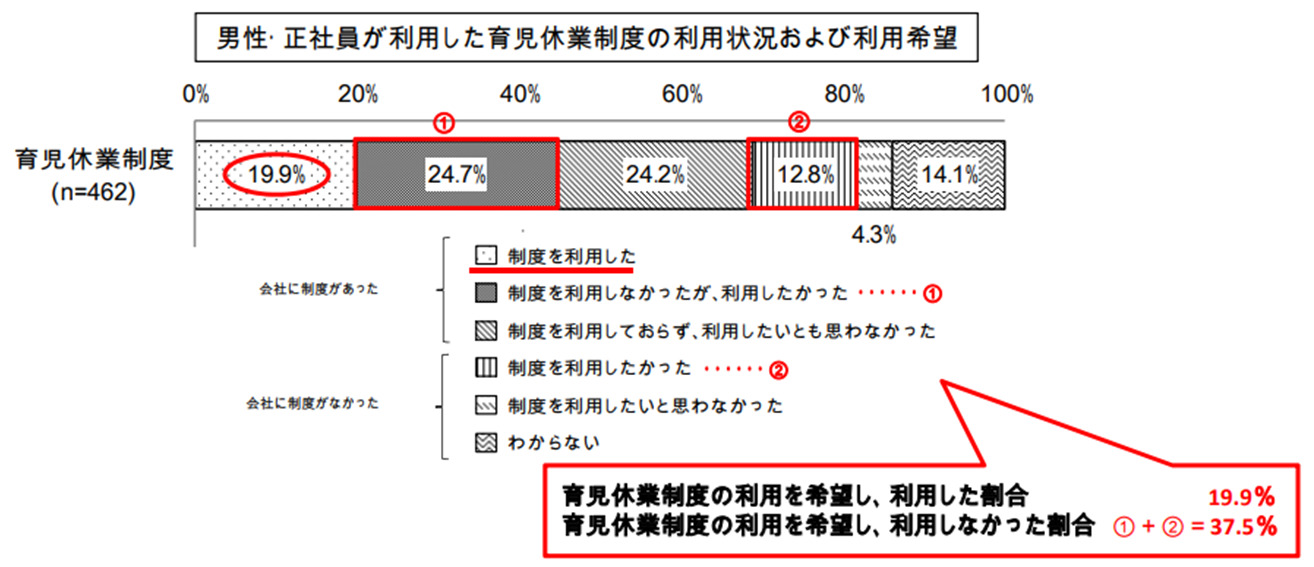
育休希望者は、57.4%。うち利用しなかった割合は、37.5%。
理由は、
・収入を減らしたくなかった
・職場の育休取得への理解がなかった
・職場が取得しにくい雰囲気だった
・自分にしかできない仕事があった
出典:
2018年三菱UFJリサーチコンサルティング「仕事と育児の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書
問題点
・労働環境
・職場の雰囲気
・個人の意識
労働環境
・過重労働
・人員不足
・当直もギリギリで回している
・他に代わる従業員がいない
基本、激務です。今の勤務体制に無理があれば、育休取得を考えることすらできません。
職場の雰囲気
・ブラック企業・医局
・会話ができない厳格な雰囲気
・相談できない人間関係
誰にも相談できず、周囲に遠慮して育休を申し出ることができません。
個人の意識
・男女共同参画の理解
・固定観念
上司も従業員も、男女共同参画の理解がない場合、育休取得者に対して、偏見が生まれ、育休を取りづらい環境になります。
家庭においても、家事・育児の協力体制が整いにくいでしょう。
数年前、男性後輩から「子どもが生まれました」と報告されました。でも、「上司や教授には報告していない」というのです。
「そうなんだ…」としか言えませんでした。
男性はプライベートを持ち込まず、仕事に邁進できるんだ。女性は妊娠・出産の報告は必須なのに…なんて思っていましたが、違います。
「言えない労働環境・職場の雰囲気」が問題なのでは、と考えます。
・仕事は当然大忙し
・若手で研鑽を積む大事な時期
・育休を取らないのが当たり前
・言い出しにくい職場雰囲気
当時、後輩はどういう思いだったかはわかりません。でも、ほんとうは育休を取りたいと思っていたとしたら…。
もし職場の雰囲気がよくて、
先輩から「何でも相談して」
上司から「〇〇君、おめでとう。育休制度を利用してもいいよ」
と声をかけられたら?
決定するのは本人ですが、とてもありがたいですよね。
解決策
目標は、
「育休希望者が、育休を取れる」社会
「男女共同参画社会」への理解と協力
個人ができること
・取得について考える
・家族と相談する
・上司と相談する
職場ができること
・制度を周知する
・従業員の希望を聞く
・労働環境を整える
・雰囲気をよくする
・育休を取得させる
個人ができること
取得について考える
希望があれば、取得について積極的に検討しましょう。
もし、周囲に取得経験のある男性がいらっしゃれば、話を聞いてみてください。
家族と相談する
育児は家族で行うもの。配偶者と相談してみてください。
上司と相談する
ご自身、家族の結論をまとめ、上司に相談しましょう。
引継ぎや人事配置の都合から、早めに申し出るのが望ましいでしょう。
職場ができること
2022年4月~育休制度の企業側から従業員への通知・取得促進は義務化されています!
制度を周知する
まず、育休制度について周知をお願いします。
厚生労働省から、雇用環境整備、個別周知、意向確認に活用できる素材が公開されており、利用できます。000852918.pdf
従業員の希望を聞く
上司の方は、従業員に声かけをし、希望を聞いていただければ幸いです。
従業員は、言い出しにくく、周囲に遠慮があるかもしれません。
労働環境を整える
当事者が育休中は、どなたかが、代理を行わねばなりません。
したがって、人員確保は必須です。そのためにも、労働環境を改善する必要があります。
勤務体制、勤務内容、当直回数、残業時間、人間関係、給与、福利厚生など、様々な問題を全面的に見直さねばなりません。
例えば、大学病院で働くと、激務にも関わらず、低賃金のため、アルバイトを兼務する場合がほとんどです。
アカデミックな機関ですが、長時間労働や収入の問題が、医局離れにつながります。
とはいえ、これらの改善はハードルが高く、すぐに解決できないのも事実。
働き方改革を推進している昨今、チーム制やシフト制の導入など、少しでも働きやすい職場環境が整うことを望みます。
雰囲気をよくする
ヒアリングを行い、よりよい職場雰囲気作りに生かしてください。
セミナーへ参加し、専門家のアドバイスを受けるとよいでしょう。
代理を行う従業員へ配慮することはもちろん、育休取得者が疎外されることがないよう、見守っていただきたいです。
育休を取得させる
育休取得を広めることは、職場にもメリットがあります。
職場のメリットは男性医師育休のメリットと注意点 にまとめました。
困難な事情があるかもしれませんが、従業員が取得を希望する場合、快く対応していただければと思います。
<PDCAサイクル>
業務改善につながる考え方。
Plan:計画
課題を検討し計画を立てる
Do:実行
内容と問題点を記録する
Check:評価
どんな成果があったか
Action:改善
次の計画に生かす
育休を取得させたら、個人・職場にとってよかった点、見えた課題を検討し、フィードバックしてください。問題点を解決し、次につなげましょう。
厚生労働省の取り組み
30年度に85%取得を目標に設定
・制度の説明、資料提供
000851662.pdf
・公表の義務化(2023年4月~)
001029776.pdf
・育休取得状況の公表と評価
・両立支援のひろば
両立支援のひろば
・中小企業向け
育児・介護支援を専門科がサポート
無料相談・セミナー
中小企業育児・介護休業等推進支援事業|パソナ
・男性の育休取得促進事業(イクメンプロジェクト)
育てる男が、家族を変える。社会が動く。イクメンプロジェクト
相談窓口
都道府県労働局に、育児休業制度の相談窓口が設けられていますので、ご利用ください。
育児休業制度等相談窓口、改正育児・介護休業法説明会、男性の育児休業取得促進等に関するセミナーについて|厚生労働省
男女共同参画について
「男女共同参画社会」って何だろう? | 内閣府男女共同参画局
まとめ
✓男性育休について
✓男性医師の育休取得率
✓取得率が低い理由
✓問題点と解決策
についてお話しました。
男女ともに、育児・仕事に参加するために。皆が生き生きと働ける環境をつくるために。
できることから始めませんか。
男性医師が育休を考えたら。いつ・どれくらいとる?メリットと注意点